三重県四日市市で毎年秋に開かれる「こども四日市」は、2004年の初開催から今年で21年目。小学生がさまざまな仕事や社会生活を仮想体験できる場として、子どもたち自身が企画・運営してきたこのイベントを映像に残そうと、ドキュメンタリー映画制作プロジェクトが進行中だ。制作費を募るクラウドファンディング(CF)は、8月15日の開始から5日で目標金額を達成したが、現在はネクストゴールに向けてさらなる支援を呼びかけている。
子どもたちが主役のまちを映画に
「こどもがつくるこどものまち」をテーマに2日間開催し、約1500人の参加者で賑わう「こども四日市」。子どもたちは、四日市市諏訪栄町の諏訪公園と商店街を舞台に、「おしごと」や「しょうばい」をして専用通貨の「ヨー」を稼ぎ、買い物や飲食を体験する。大人にやらされるのではなく、自らアイデアを出し、試行錯誤してやりたいことを形にする楽しさを大切にしてきた。

イベントの映像化は、「経験を形に残したい」という声が、小学5年から中高生、大人になったOBらで構成する実行委員会「GOLD市民会議」で上がったことがきっかけ。長年会場として親しんだ諏訪公園の改装工事が始まる前に、その姿を含めて記録することになった。プロジェクトリーダーの小林渚さんは「制作段階から多くの方に関わってもらうことで、映画も子どもたちの思いもより広く伝わると考えた」と語る。
子どもたちの声から生まれたテーマソング
映画の主題歌づくりも子どもたち主導で行われた。6月と7月に開かれた会議では、子どもたちの実際の体験や思いをもとに歌詞のフレーズ集めを実施。「最初は大変ハローワーク」「親が問題解いたこども学校」「ガムテープをはがす音」などの意見が出され、会議に参加した約15人の「GOLD市民」の子どもたちや学生らで一つの歌詞にまとめた。

谷祐汰さん(中3)の出した「失敗も挑戦もいつか思い出になる/経験は人生のピースとなる/自分の未来を自らで創れ/ここでは何でもできる/心はいつだってこどもなんだから/笑って楽しめ」という一連のフレーズには、会議の参加者全員が沸き立ち、サビ部分にまるごと採用することに。
作曲を担当したのは、小学4年から「こども四日市」に参加し、現在は運営に携わる圡屋有彩さん(18)。子どもたちから寄せられた「元気いっぱいの曲にしたい」「ラップを入れたい」「しんみりと落ち着いたパートも」などの要望を反映させ、静かな導入からにぎやかなサビ、最後はしっとりと締めくくる展開に仕上げた。「こども四日市」の2日間を音楽で追体験できるかのような構成になっている。

8月24日には子どもたちによるレコーディングが行われた。最初は緊張した面持ちだったが、パート練習を重ねるうちに表情が和らぎ、自信もついていった。やがて「もっと高みを目指してく?」「目指そう!」と声を掛け合いながら、自主的に何度もテイクに挑戦する姿が見られた。
完成特別試写会、満員を目指して
制作にはCFで支援を募っており、最初の目標金額10万円の達成以降は、次の目標「2026年5月24日(日)に予定している完成特別試写会を満員にしたい」への協力を引き続き呼びかけている。試写会の会場は約30名がゆったり入れる規模で、まずはあと十数人の支援を集めることを目指している。
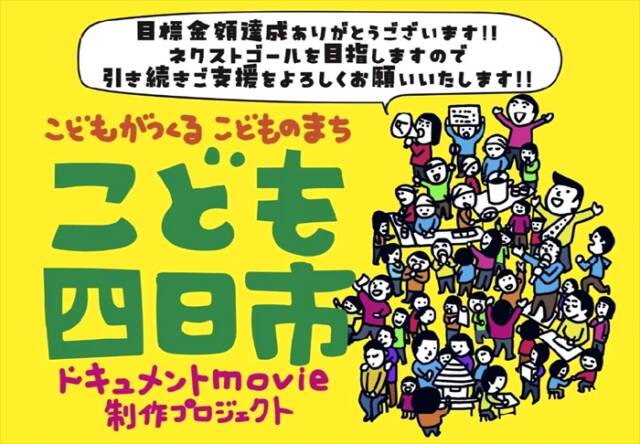
映画はこれまで撮りためた映像と、今年11月に行われる「こども四日市2025」での本格撮影を経て編集する予定だ。来年3月に関係者向け試写会を実施し、そこでの意見を反映して最終仕上げを行う。完成後は四日市市内の会場での上映を皮切りに、全国の希望者向けにも上映会を企画していきたいという。
寄付はCAMPFIRE特設ページ(https://camp-fire.jp/projects/view/869915)で、9月30日まで受け付けている。リターンには、エンドロールでの名前掲載や、完成特別試写会・トークセッションへの招待、オリジナルグッズなどが用意されている。
小林さんは、「こども四日市には『正解』は用意されていません。子どもたちが自分で考え、失敗しても工夫して新しいアイデアが生まれる、そんな場所です。この映画を通して、子どもたちの逞しさや活動の面白さを広く知ってもらえたら」と話す。支援の輪と子どもたちの思いが重なって、映画の完成がいっそう楽しみになりそうだ。









