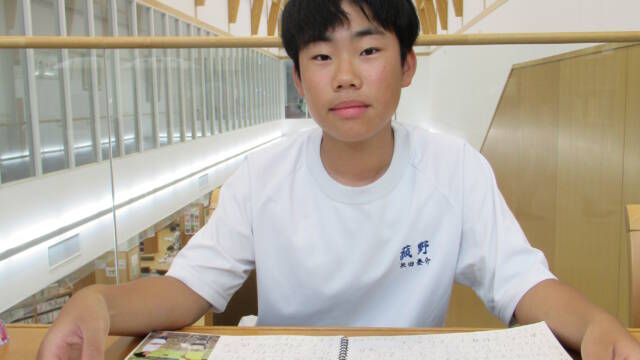未記載種かも――ハラビロカマキリに魅せられて
三重県立四日市農芸高校をこの春に卒業した椎名奏衣さん(19)が、展足板に横たわる昆虫の羽や脚の向きをピンセットで整え、慎重に針を打っていく。在学中にマレーシアのボルネオ島で初めて採集して以来、注目しているハラビロカマキリの仲間(Hierodulinae gen. sp.)だ。「今のところ種類が不明で、未記載種の可能性があるカマキリなんです」と目を輝かせる。
アリとの出会いから始まった、昆虫への果てなき好奇心
昆虫との出会いは2歳のころ。小さな手でアリに触れたのが原点だった。 保育園時代にはオオカマキリ(Tenodera sinensis)に夢中になり、小学生になると「昆虫博士」と呼ばれるように。
中学の修学旅行で訪れた鳥羽市の答志島では分類が難しいフキバッタ(Parapodisma sp.)を、志摩市の横山展望台では珍しいサツマヒメカマキリ(Acromantis satsumensis)を発見。「持ち帰って標本にしました。今も理科室に残っているんじゃないかな」と笑う。

ボルネオ島で出会った「謎のカマキリ」
高校時代は3度にわたり、昆虫の宝庫と呼ばれるボルネオ島へ渡った。夜間にライトトラップを設置し、集まった昆虫を丁寧に採集。数は百匹を超えた。
中でも冒頭のカマキリ(体長約7㌢から8㌢)は、日本に生息するハラビロカマキリ(Hierodula patellifera)より全体的に大きく、前脚や腹部が太く、メスの上翅の形状が丸みを帯びていることから、分類が難しい存在だ。論文や標本写真が少なく、正確な分類、あるいは新種記載を目指し、椎名さんは留学を決意した。

未来の研究者、羽ばたく19歳
採集したカマキリは、3年生の時の課題研究「日本とボルネオ島のカマキリ調査」でも大きく取り扱った。日本では外来種を含め14種1亜種しかいない一方、ボルネオ島では椎名さんが確認できただけで30種に上った。なぜ日本の方が少ないのか――その疑問を出発点に、データ整理と考察を重ねた。
高校卒業後の今年5月には、4度目の調査に赴いた。現在はマレーシア・サバ大学熱帯林学部への進学を見据え、語学留学している。
「昆虫の宝庫と呼ばれるボルネオ島で、多くの固有種を目にしたいし、少しでも分類を進める一助となりたい」と抱負を語る椎名さん。幼い頃の小さな好奇心は今、研究者としての確かな一歩へと変わった。